アフィリエイト広告を使用しています。
こんにちは。
今回は子どもたちが夢中になって遊ぶおもちゃの紹介をしていきたいと思います!
遊びのなかで夢中になるって難しいですよね…。
今の時代は動画やゲームがたくさんあって、魅力的ですものね!
ボクは動画、ゲームなどは肯定派です。
自分の娘にも小3でPCを買い与えて、今では自分でアニメーションを作っています。
ボクは全くできないですが、本人は動画を見て学んだ、とのことでした。
「たくさん本を読みなさい」の時代から「たくさんネット、動画を見なさい」の時代に移ってきているんですかね?
当然危険もありますが、そこは一緒に約束をして、保護者が管理していけば大丈夫です!
さて、少しズレてしまいましたが、今回はそのような電子機器ではない玩具の紹介をいたします。
1,カプラ
2,粘土
この2つを紹介していきますね。
では、まず1つめの「カプラ」です。
これはなかなか一般的には知られていないかもしれませんね。
でも、保育業界では知らない人はいないのではないか、というほど有名だし、だいたいの園に置いてありますね!
単なる木の板の積み木のように見えるのですが、これがかなり奥深いものなんです!
まず、ボクが注目したのは材質です。
厳選した松で作っているので、積み木が崩れた時の音がとっても心地よい音なんです!
カプラの研修を受けた際に聞いたのですが、木琴と同じ周波数の音なんですって!
崩れる時も楽しみにできる積み木、なかなか面白いですよね。
次に注目するところは精度です。
公式HPには「一本積み」というコーナーがあって、縦に何本積めるか、というチャレンジ企画があります。
最大で12本積んでいるツワモノのいますが、ボクは8本が限界でした…。
これ、大人もちょっと夢中になります。
この細い板でもここまで積めるほど精度が高い、というのを実感しました。
最後に作品の幅です!
実はネット検索をすると本当に様々な画像が出てきます。
どうやって作るかを頭の中で想像して、設計していくことで子どもたちの空間認知能力を育むこともできます。
実際に保護者が一緒に作ることで組み方を覚えて、自分流にアレンジして、さらに高度な作品にチャレンジする、なんていう一連の流れも見えてきますね☆
でも、こんなに大きいと片付けや置き場所が…
そんな方にはこれ!
「チャレンジカード」という物が入っていて、その形を作る、というものなのですが…
まぁ、難しい!
でも、大人も夢中になって遊べるほどおもしろいですよ♪
次に「粘土」です。
先ほどのカプラと違って、誰しもが一度は触れたことのある遊びだと思います。
家にもあるけどべたべたになるし、片付けも大変でなかなか使用頻度が少ないのではないでしょうか?
でも、粘土ってすごいんです!
まず、この画像をご覧ください。

このちょっと不気味な人形は「ペンフィールドのホムンクルス」というものです。
これは「体の各機能が大脳の中でどれぐらいの領域を司っているか」というものです。
なかなか難しい話にはなってくるのですが、要するに手(指先)と口は脳にとって大部分を割いている、ということです。
実はボクは大学時代に脳と心の研究を行いました。
その時にこのホムンクルス人形を目にしていましたが、まさか保育士としてこれをもう一度見ることになるとは思ってもいませんでした。
目や耳がまだ発達しきっていない赤ちゃんが口の中に物を入れて様々なことを確かめるのはそれだけ口の中の感覚が研ぎ澄まされているから、ということです。
そして、手や指先も同じです。
ここをたくさん動かして刺激することで脳の発達にも大きく影響してきます。
さぁ、ここで本題の「粘土」に戻りましょう!
粘土は指先の感覚がかなり重要ですよね!
強くやりすぎてしまっては壊れてしまいますし、優しくやりすぎても形を作れない。
その力加減なども学ぶことができます。
そして、ボクが粘土推しなのは何よりも「イメージをそのまま形にできる」という点です!
ただ、やはりネックなのはあのベタベタですよね…。
そこで、これ!
え?業者じゃん…。
いやいや、プロが使ってる汚れ防止の定番商品です!
どうです?こう言い換えるとちょっと興味がわきません?笑
冗談は置いておき、本当に凄いんです!
机にこれを貼って反対側は粘土のフタでも置いておけば机が汚れることはないのです!
しかも、作り終わってからはそのまま捨ててもそこまで高価なものでもないので気にならないです♪
また、お子さんが壮大なスケールで作ったジオラマのようなものになってもそのままビニールごと移動させる、なんてこともできます!
これで粘土に対するデメリットが大幅に解消されて、脳の発達、というメリットばかりになりましたね!
最後に、カプラも粘土もぜひ初めのうちは保護者の方も一緒に楽しんでみてください!
保護者が楽しく遊んでいる姿を見て、子どもたちも興味を持ってその玩具に接します。
そして、楽しく会話をしながら遊ぶことでその楽しさも倍増していきます。
この記事を読んで子どもたちと楽しい時間を過ごせてもらえたら嬉しく思います!
こんな記事も書いています。あわせてお読みください!
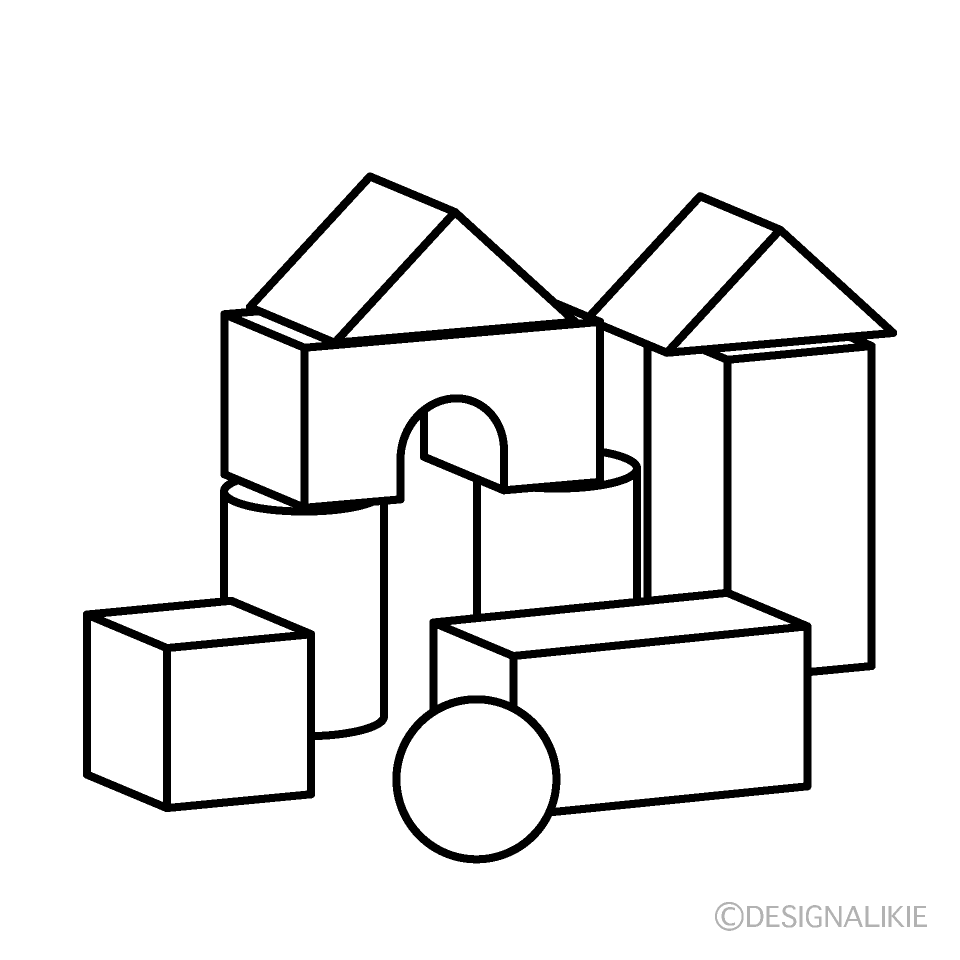


コメント